夜遅く、ふと街を歩いていると、ビルの一角から煌々と明かりが漏れている。そこが塾だと気づくと、「お、がんばってるな」「遅くまで生徒に対応してるのかな」と一瞬思うかもしれません。
けれど、見る人が見れば、まったく違う印象を持つこともあります。
「ああ、この塾の中の人、仕事が遅いんだな」「時間をうまく使えていないな」
そんなふうに“見抜かれて”しまうのです。
実際、流行っている塾や、支持されている教室の教室長をよく観察すると、「仕事が早い」「無駄な時間を作らない」タイプが多いと感じます。今回は、“定時で帰れる塾”がなぜ集客にも良い影響を与えるのか、その理由について考えてみましょう。
いつまでも教室に残っていませんか?
もちろん、夏期講習の前後や、テスト対策期間などは一時的に遅くなることもあります。保護者対応や講師との面談が詰まって、予定通りに帰れない日もあるでしょう。
しかし常に日をまたぐまで教室に残っている…。そんな状態が常態化しているとしたら、それは“熱心”ではなく“段取り不足”のサインかもしれません。
毎日の仕事に優先順位をつけ、やるべきことを前倒しで進め、集中して取り組む。こうした習慣を身につけることで、定時で仕事を終えることは十分に可能になります。
そして、この「定時で帰れる状態をつくれる教室長」は、結果的に教室をうまく回せる人でもあるのです。
段取りの良さは、保護者にも伝わっている
ここで注目したいのが、“お客様である保護者の目”です。
塾のターゲット層として、経済的に余裕のある家庭、いわゆる「富裕層」を意識している教室は少なくないと思います。実はこの層の方々は、我々が思っている以上に「教室運営の雰囲気」や「教室長の働き方」にも敏感です。
というのも、富裕層の方の多くは自らも経営者だったり、会社の管理職だったりと、組織をマネジメントする立場にあることが多いからです。
そういった方々は、教室にふらっと訪れたときに、教室長が疲れた顔で深夜まで働いているような雰囲気を察すると、こう思うかもしれません。
「この人、自分で自分の仕事すらコントロールできていないのでは?」
逆に、教室がいつも整然としていて、教室長が時間通りにキビキビ動いている様子が伝われば、「きちんと回っているな」「この教室は信頼できそうだ」と感じてくださる可能性が高まります。
“段取り力”は、教室長の武器
教室運営において、仕事ができるかどうかは「スピード」と「優先順位の判断力」で決まります。
・このタスクはいつまでに終わらせるべきか?
・どこまで自分でやり、どこから人に任せるべきか?
・今この時間、何をすべきか?
これらを常に考え、実行できている教室長は、必然的に仕事の密度が上がり、時間の使い方がうまくなります。そしてそれが、「残業せずとも結果を出せる教室」につながっていくのです。
“忙しそう”な教室は実は魅力がない?
意外かもしれませんが、「いつも忙しそうな教室」ほど、問い合わせ数が減る傾向があります。
なぜなら、「今入っても対応してもらえなさそう」「講師や教室長が疲れていて余裕がなさそう」といった印象を与えてしまうからです。
一方で、落ち着いた雰囲気の中に活気があり、教室長やスタッフの動きに余裕が感じられる教室は、「この塾なら安心して預けられる」と思ってもらいやすくなります。
つまり、仕事を定時で終えられる教室長は、教室の“空気”までコントロールできる人だということ。空気感こそが、実は集客にも影響する大事な要素なのです。
「仕事を早く終える」は、経営戦略である
定時で帰れる塾は、単に働き方改革の話ではありません。それは、塾経営における**“戦略”**でもあるのです。
・生徒や保護者に安心感を与える
・講師の離職を防ぐ
・教室長自身が常に冷静に判断できる余裕を保つ
これらすべてが、教室経営の基盤を安定させる要素です。
ですから、「定時で帰ること」は恥ずかしいことでも、サボりでもありません。それは、「私は計画的に教室を運営できています」という無言のメッセージになり、地域からの信頼につながっていくのです。
最後に:定時で帰る教室長は信頼される
塾の仕事は終わりがありません。生徒対応、保護者対応、講師管理、進路指導、イベント運営…。やろうと思えばいくらでも仕事は出てきます。
だからこそ、意識的に「仕事の質を高め、時間を意識する」ことが必要です。
定時で帰れる教室長は、“時間の価値”を知っている人。
時間の価値を知っている人は、“人の時間”も大切にできる人。
そういう教室長が、結果的に生徒・保護者・講師から信頼され、塾としても選ばれる存在になっていくのです。

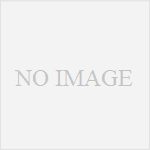
コメント