「午前中に、今日の勉強は済ませちゃいなさい!」
よかれと思って、つい口にしてしまうこの言葉。しかし、長年、何千人という子どもたちの「やる気の浮き沈み」を目の当たりにしてきた私から言わせれば、この一言こそ、子どもの学ぶ意欲を根っこから腐らせてしまう、非常に危険な”呪い”の言葉になりかねないのです。
今日は、なぜこの言葉がNGなのか。そして、子どものやる気に科学的に火をつける「正しい声かけ」とは何なのか。塾経営のプロとして、ストレートにお話しします。
1. なぜ「済ませなさい!」はNG? 言葉が脳に送る“罰ゲーム”信号
まず、言葉の響きです。「済ませる」とは、本来イヤなこと、面倒なことに使う言葉ですよね。これを聞いた子どもの脳は、瞬時に「勉強=罰ゲーム」と判断します。
そうなると、やる気の源である脳の報酬系(ドーパミン)がまったく働きません。ドーパミンは「楽しい!」「できた!」という達成感とともに放出される、脳のガソリンです。エンジンのかからない車に「走れ!」と叫んでも無意味なのと同じで、子どもがやる気を出せないのは当然なのです。
さらに厄介なのが、親御さんの「やれやれ感」は、そっくりそのままお子様に伝染するということ。親が「勉強はイヤなもの」という前提で接しているのに、子どもだけが「勉強は楽しい!」と感じることはありません。この“負の空気”こそが、子どもの学ぶ意欲を静かに蝕んでいきます。
2. 「やりなさい!」を100回言うより、親が1冊の本を読む方が効く理由
「じゃあ、どうすればいいんだ!」
答えは驚くほどシンプルです。
「『勉強しなさい!』と叱るより、親が楽しそうに学ぶ姿を見せる」
たったこれだけです。子どもは、親が言うことよりも、親がやっていることを見て学びます。リビングで親が夢中で本を読んでいる姿は、「学ぶことは楽しいことなんだ」という何より雄弁なメッセージになります。
これは感覚的な話ではありません。国際的な学力調査PISAでも、家庭の蔵書数や親の読書習慣が、子どもの学力と強い相関があることは繰り返し示されています。本棚は最高のインテリアであり、読書する親の背中は、最高の教材なのです。
3. 子どものやる気を爆発させる「自己決定」の力
結局のところ、子どものやる気を動かす最強のエンジンは、本人の「自分で決めた!」という感覚以外にありません。これを心理学では「内発的動機づけ」と呼びます。外からアメとムチで無理やり動かそうとすると、そのうちエンジン自体が壊れてしまいます。
私たちの役割は、子どもの手綱を握って管理することではなく、子どもが自分でハンドルを握れるようにサポートすること。これを「自律支援」と呼びます。難しく考える必要はありません。今日から使える、やる気を引き出す「自律支援」4点セットをご紹介します。
① 選択肢を渡す
NG例:「算数の宿題やりなさい!」
OK例:「先に算数と国語、どっちから片付けたい?」
命令されると反発したくなりますが、「自分で選んだ」という感覚だけで、行動は「やらされ仕事」から「自分のプロジェクト」に変わります。
② 理由を共有する
NG例:「いいから早くやりなさい!」
OK例:「これを終わらせておくと、午後は心おきなく公園に行けるね!」
行動の先にある「良いこと」を具体的に示すことで、子どもはその行動の意味を理解し、納得して動くことができます。
③ 感情を承認する
NG例:「面倒くさがらないの!」
OK例:「面倒だよね。わかるわかる。お母さんも仕事でそういう時あるよ。」
「面倒」という気持ちを否定せず、一度受け止めてあげる。これだけで子どもは安心し、「でも、やらなきゃな」と、次の一歩を踏み出す心の余裕が生まれます。
④ 手を出しすぎない
NG例:「やり方が違う!こうやりなさい!」
OK例:「まずは自分で計画立ててごらん。もし詰まったら、ヒントだけ出すから呼んでね。」
過干渉は、子どもの「自分でできた!」という達成感を奪う最悪の行為です。必要な支えだけを用意し、あとは信頼して任せる。これが子どもの自律性を育てます。
4. 「朝勉」は万能じゃない?科学が示す子どもの集中ゴールデンタイム
そもそも、「午前中に勉強する」というスタイルが、全ての子にとって最適とは限りません。
人には「朝型」「夜型」といった体内時計(クロノタイプ)があり、特に子どもや若者は夜型に傾きやすいことが知られています。夜型のフクロウに、朝型のヒバリと同じ時間に活動しろというのは酷な話。脳がまだ眠っている状態で勉強させても、効率が上がらないのは当然です。最新の大規模な研究でも、学力テストの成績は「正午前後にピークを迎える」という結果が示されています。
大切なのは、「朝が正義」と決めつけるのではなく、「うちの子のゴールデンタイムはいつだろう?」と一緒に探してあげる視点です。午前中に軽いウォーミングアップをし、最も集中できる時間帯に難しい課題に取り組むなど、ぜひ色々試してみてください。
まとめ:言葉を変えれば、子どもの学びの色が変わる
これまで見てきたように、子どものやる気を引き出す鍵は、私たちの何気ない「言葉」と「関わり方」の中に隠されています。
- 「済ませなさい」より、「今日はどの順番でやる?」
- 「早くやりな なさい」より、「お父さんも読書するから、一緒にやろう」
- 「終わった?」より、「一番おもしろかったところ、あとで教えて」
学びは、子ども自身が走り出す営みです。私たち大人の役目は、罰ゲームの会場を整えることではなく、子どもが「走ってみたい!」と思えるような、明るく魅力的なスタートラインを用意してあげることなのです。

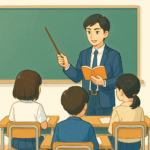
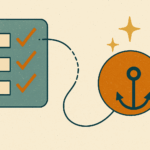
コメント