私が教室長として徹底してきたことの一つに、「他塾調査」への向き合い方があります。新年度が始まると、近隣の競合塾から、いわゆる偵察目的の来訪者が現れるのは業界の常です。
結論から言えば、私の対応は一貫していました。
他塾調査だと分かっていても、いや、分かっているからこそ、いつも以上に丁寧にもてなし、手の内を堂々と見せる。これにつきます。
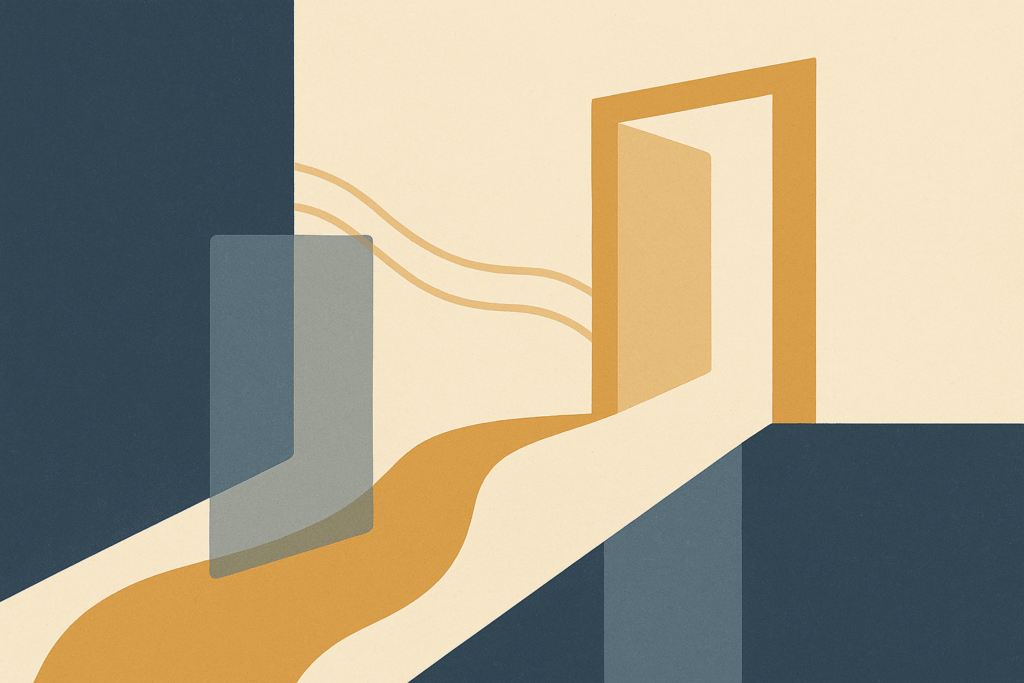
来訪者が競合だからこそ、誠実さで圧倒する
春先、保護者にしては若すぎる男女が、少し緊張した面持ちで教室に入ってくる。大手塾が新入社員研修の一環で、近隣教室の“現地ヒアリング”を課しているケースです。現場の人間であれば、その雰囲気で大方の察しはつきます。
ここで多くの教室長が選択しがちなのが、警戒心を前面に出した、ぞんざいな対応です。資料は渡さない、質問には最低限しか答えない。しかし、これは三流の対応であり、自らの首を絞めるだけの愚策だと私は断言します。
相手が競合だからこそ、こちらの運営レベルや教育哲学を、揺るぎない“体験”として持ち帰ってもらうことにこそ価値があるのです。私はむしろ、そうした来訪者を歓迎し、通常の入塾面談と何ら変わらない熱量で、こちらの仕組みや考え方をオープンに共有してきました。
私が実践した「大公開」スタイルとその本質
塾という業態は、構造的に閉鎖的になりやすいものです。しかし、私はその逆をいくことを自らに課していました。
授業見学は、防犯と他の生徒の学習環境に最大限配慮した上で、原則として受け入れる。入塾面談で何を語り、入塾後にどのようなフォローアップを行うのか、そのシナリオやテーマまで包み隠さず説明する。漫画や私物が放置された生活感あふれる事務スペースではなく、いつ誰に見られても恥ずかしくないよう整理整頓を徹底する。
「いつ見られてもいい状態」を日常にすること。これこそが、小手先の広告や割引キャンペーンとは比較にならない、最も強力な差別化戦略です。なぜなら、オープンにできるということ自体が、日頃の教室運営が健全である何よりの証拠だからです。
※補足ですが、当時は講師の服装や身だしなみ、所作(授業中に足を組まない等)についても厳格な基準を設けていました。現代の価値観に照らせば柔軟に見直すべき点もありますが、「明確な基準をチームで共有し、守る」という行為そのものが、運営品質の根幹を成すという考えは今も変わりません。
「見せられない教室」が抱える、構造的な問題
そもそも、なぜオープンにできないのか。その理由は、例外なく日常の運営管理に潜んでいます。
講師たちが授業外の時間にだらけている雰囲気、整理されていない机や本棚、一貫性のない指導姿勢。外部の人間を安易に入れられない教室は、こうした日々の小さなほころびが、無視できないレベルまで積み上がっているのです。
来訪者の有無にかかわらず、「ありのままの日常を見せられる」状態を維持する。これができれば、他塾調査など恐れるに足りません。
手の内を明かせば、模倣されるのか?
仕組みやノウハウを話したら真似されるのではないか、と心配する方もいるでしょう。しかし、私の経験上、その心配は無用です。
本質的な運営力や指導力は、決して容易に模倣できるものではありません。
仮に面談のシナリオや特典のアイデアを持ち帰ったとしても、それを血肉として動かす組織文化や人材育成の土壌がなければ、決して同じ結果にはならないのです。むしろ、こちらが圧倒的な自信をもって全てを開示することで、相手は「このレベルには、簡単には追いつけない」という事実を痛感することになります。力の差を、理屈ではなく“体験”として理解してもらう。それこそが、こちらの本当の狙いでした。
ある同級生の教室が、私に教えてくれたこと
ある時、他塾調査の一環でとある教室を訪れた際、忘れもしない出来事がありました。応対してくれた教室長が、偶然にも大学時代の同級生だったのです。
私はすぐに身分を明かし、お互いにとって有益な情報交換がしたいと申し出ました。しかし、彼の対応はガードが固く、説明は最小限、授業見学も当然のように断られました。その教室が「見せられる状態」にないことが、その短いやり取りの中から透けて見えたのです。
その後、残念ながら彼の教室はほどなくして閉鎖されました。理由は複合的だったでしょうから一概には言えませんが、「外部に見せられる日常」を構築できていなかったことと、運営の継続性には、決して小さくない相関がある。私はそう感じています。オープンにできるということは、それ自体が健全な運営を維持するための、最も効果的な自己点検でもあるのです。
「見せられる日常」こそが、最強のブランディング
他塾調査の来訪は、自らの運営レベルを試される“抜き打ちテスト”などではありません。むしろ、自塾の価値を地域に示す絶好の機会です。
今日からできることは、シンプルです。
常に外部の視線を意識し、見学OKを前提とした日常運営を整える。面談や入塾後のフォロー体制を言語化し、誰にでもよどみなく説明できる状態にする。事務スペースの整理整頓を仕組み化し、講師の指導姿勢についても明確な基準をチームで共有する。
そして、もし競合の来訪者だと分かったなら、最上級の接遇で迎え、我々の教育の“体験価値”をたっぷりと持ち帰ってもらう。
「見せられる日常」を作り上げること。それは、どんな広告よりも雄弁に自塾の価値を物語る、最強のブランディング活動です。どうせ来訪があるのなら、それを最高のショールームデイにしてしまいましょう。

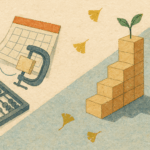

コメント