教室長は“担任役”――アルバイトでは届かない設計と責任
個別指導の現場で、アルバイト講師は「自分が大学受験を乗り切った」という一つの成功事例の延長で語りがちです。「数学は勉強していれば勝手に伸びる」といった個人の経験談は、ある生徒には有効でも、他の生徒には当てはまりません。現場で求められるのは、個人の体験談ではなく、生徒を“実際に伸ばす”ための設計と、結果に対する責任です。
そこで教室長の仕事は、模試の帳票を起点に一人ひとりの学習の物語を組み立てることにあります。単に点数の上下を指摘するのではなく、次の一歩に接続する具体的な言葉と行動をセットで提示します。
“もっともらしさ”を捻出する――模試帳票は生徒を動かす物語の素
私が面談で多用したのは、確率(数学)から現代文(国語)への橋渡しという手法です。例えば、国語が苦手な生徒が確率の大問で高得点を記録した際、このように伝えます。「確率は文章の読解力で解く分野だ。ここで点が取れたのは、君に現代文が伸びる資質があることの証明に他ならない。必ず伸びる」。
これは一見、無責任な放言に聞こえるかもしれません。しかし、根拠があるように聞こえる前向きな解釈は、生徒の行動を変えます。実際にこの一言で、宿題の質や読解への取り組み方が変わっていくのです。ここでの要点は、「事実(得点)から解釈(資質)へ、そして次行動(学習タスク)へ」と、思考を三段階で飛躍させることにあります。
スケールの壁――大教室運営で見えた限界
在籍200名の大教室では、教室長一人の面談だけでは限界が訪れます。理想は、講師全員が“その気にさせる”という働きかけを再現できる状態です。面談の型や言い回し、帳票の読み方をナレッジとして共有し、訓練しない限り、属人的な面談は組織としてスケールしません。
そのために、帳票から必要な読解力を見立て次回課題を設定するテンプレートや、行動を促すための肯定的な決めゼリフ集、そして事実・解釈・次行動を一行でまとめる面談メモの書式といった“言葉の型”を整備し講師に配ることで、アルバイト講師でも一定水準の面談が実施できるようになります。
痛い失敗の記録――感じ方は相手が決める
ある日、中学3年生の男子生徒と長めの面談を実施しました。数日後、本社に保護者から「軟禁され、責め立てられた」とのクレームが入りました。面談の意図がどうであれ、どう感じたかを決めるのは相手です。この件はエリア長による謝罪をもって対応し、当該生徒は退塾に至りました。こちらに言い訳の余地は一切ありません。
この一件を境に、私は面談の運用を全面的に見直しました。もし同様の訴えが女子生徒から「セクハラ」という形でなされていたら、教室も私自身のキャリアも終わっていたかもしれないという危機感を、骨身に刻み込みました。
面談運用の“安全設計”――衆人環視・短時間・記録
この失敗以降、私は面談の運用ルールを徹底しました。まず場所の可視化として、受付カウンター越し、あるいは面談室のドアを全開にし、外から会話の様子が見える、または聞こえる状態を標準としました。次に時間の可可として、面談は10分から15分で区切り、終了時刻をあらかじめ伝えます。延長が必要な場合は保護者同席のもとで再設定する形を取りました。さらに記録の可視化として、面談内容は「事実・解釈・次行動」の3行でメモを残し、日時、場所、在室者も明記します。この要点は必要に応じて保護者へも共有しました。加えて在室者の可視化として、性別や学年を問わず、同フロアに別の講師が常駐している時間帯にのみ面談を実施し、ワンオペレーションになる時間帯の個室面談は禁止としました。最後にアジェンダの可視化として、面談の冒頭に「今日やること」を3点で言い切り、終了時には「決めたこと」を3点で復唱します。これにより、会話が私語や詰問といった方向へ逸れる流れを構造的に防ぎました。
これらは自分を守るためだけでなく、生徒と保護者を守るための“場の品質管理”に他なりません。
面談を“やらない塾”にも効く代替の仕組み
面談の頻度を上げずとも、“その気”をつくる仕組みは構築可能です。一つは、フィードバックカード方式です。模試返却時に個票へ付箋を三枚貼り、それぞれに「よかった事実」「解釈」「次行動」を一行ずつ記します。講師全員が同じ書式で実践し、教室長は言い回しの校正に専念します。あるいは、3分アナウンス方式も有効です。授業冒頭の教室長アナウンスで「確率で読解力が出ている人は現代文の伸びしろがある」といった共通の物語を全員に流し込みます。また、スタンプ課題方式も考えられます。「次行動」を小さな行動習慣にまで落とし込み、スタンプやチェック欄で可視化するのです。講師はスタンプを押すだけ、教室長は集計と称賛に徹することができます。
まとめ――“言葉の設計”と“場の設計”が面談のすべて
言葉の設計とは、帳票という事実を前向きに再解釈し、次行動に直結する一言を用意することです。場の設計とは、衆人環視・短時間・記録というルールで、面談を安全で再現可能な業務にすることです。そしてスケールの設計とは、言葉の型や書式、運用ルールを講師に配り、教室全体で生徒の“その気”をつくる体制を構築することにあります。面談は決して叱る場ではありません。事実を再解釈し、次の一歩を決める場なのです。私の成功と失敗が、皆様の教室運営のケーススタディになれば幸いです。
付録:すぐ使える“3行メモ”の雛形
事実:__(例:確率の大問4で16/20点)
解釈:__(例:文章読解で答案を組み立てる力がある=現代文の伸びしろ)
次行動:__(例:現代文は音読3分+設問先読み1分を毎回、1週間で計5回)


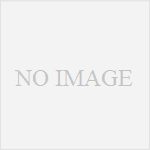
コメント