スーパーの携帯ブースで気づいたこと
近所のスーパーで、携帯代理店のブースが出ていました。
若いスタッフさんがティッシュを配り、勢いのある口調で「今ならキャッシュバック!」「今日決めましょう!」と次々に畳みかける。A4のメモ用紙に金額を書き出し、メリットをこれでもかと押し出してくる——。
その様子を眺めながら、私ははっきり確信しました。塾の現場には、この手の“まくし立て式の営業”は要らない。
携帯販売は一期一会になりがちで、苦情の矛先もキャリア本体へ向かいます。対して塾は、入会後こそが本番。学習成果・保護者対応・習慣化の伴走——すべてが長期の信頼で評価されます。短期の説得テクニックが効くどころか、むしろ逆効果になることが多いのです。
結論:塾の面談で語るべきは「上がる理由」ではなく「上がらない条件」
私が大手個別指導の教室長だった頃、入塾面談ではデメリットから先にお伝えしていました。
「通えば誰でも上がる」とは言いません。むしろ、こういう条件なら上がらない——これを具体例とともに列挙します。
欠席・振替が常態化するタイプ 勉強が“第二優先”のままだと、計画が崩れ、学習の連続性が断たれて伸びません。振替制度が充実していても、休み癖は成果の最大の敵です。 本人に“やる理由”がない状態 親が主導で連れて来た、面談中も終始不機嫌、問いかけに答えない——この段階では入会をいったんお断りします。本人が必要性を腹落ちできてから再訪していただく方が、結局は全員幸せです。
このスタンスは一見“営業下手”に見えるかもしれませんが、長期で見ると解約率が下がり、口コミの質が上がる。短期の“数字”よりも、地域からの信頼残高が積み上がります。
携帯販売と塾の決定的な違い
関係の性質:携帯は契約=終点になりやすい。塾は入会=起点。 成果の時間軸:携帯の満足は即時(料金・端末)。塾の満足は遅効性(学力・習慣)。 口コミの比重:塾は地域密着・紹介依存度が高く、悪評の払拭に年単位で時間がかかる。
ゆえに、勢いで契約を押し切ることは、塾では自傷行為になりやすいのです。
私が現場で実践していた面談の型
1) まず「合わないケース」を明確化
最初に“入会してはいけないケース”を伝えます。これでミスマッチを先に潰す。相手の表情が緩み、こちらへの信頼も上がります。
2) 次に「ここで伸びるための前提」を合意
通塾頻度、宿題量、テスト前の運転(増コマ/自習の使い方)、欠席時のルールなどを約束事として合意します。
「うちをどう使えば上がるか」を具体に落とすことが、唯一の“営業トーク”です。
3) それでも違和感が残るときは“断る勇気”
面談で違和感(温度差・優先順位の不一致)が残る場合、入会は見送りにします。短期の売上は減っても、将来のトラブルコスト(不満・クレーム・悪評)は確実に減ります。
よくある反論への答え
Q. 営業しないと入らないのでは?
A. 「営業しない」のではありません。「誤差のある期待を積み上げない」だけです。テクニックで“背中を押す”のは最後の一点突破で十分。最初の段階は現実の条件合わせに全振りした方が、継続・成果・紹介の三拍子が揃います。
Q. デメリットを言うと逃げませんか?
A. 逃げる方は、逃げて正解です。入会後の不満として必ず戻ってきます。最初に逃す勇気が、教室全体の学習濃度を高めます。
面談でそのまま使えるフレーズ例
「ここは**“入ってから上がる場所”**です。だからこそ、上がりにくい条件を先に共有しますね。」 「欠席や振替が多いと、効果はガクッと落ちます。その運用だと、正直ここではおすすめできません。」 「今日は入会を急ぎません。必要だと思えたタイミングで、もう一度来てください。そこからで十分です。」
(ポイントは断定の言い切りと相手の選択権を尊重する言葉の並置です。)
まとめ:数字より“選別”、テクニックより“納得”
営業トークの多弁は、塾では効かない。 デメリット先出しと前提の合意が、成果と継続の土台。 違和感があれば断る勇気を。短期の数字より、地域の信頼残高を積む。
塾はアフターサービスそのものを提供する業態です。
だからこそ、面談は「口説く場」ではなく、「条件を合わせ、納得で始める場」。
ここを外さなければ、営業トークが少なくても——いや、少ないからこそ——強い教室になります。

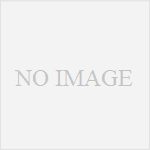
コメント