若者は夜に強い。だから、朝イチの授業をやめてみる
外で収録していたら車の音がビンビン。そんな雑踏の中でふと浮かんだ小話を、今日はエッセイとして置いておきます。
私は若い頃、とにかく朝が苦手でした。10代から20代の終わりまで、社会人になっても遅刻“らしきもの”をやらかす。ところが30代、40代と年を重ねるにつれて、自然と朝方に移行していった。努力の成果というより、体のスイッチがじわっと切り替わった感覚に近い。
ここで言いたいのは、「遅刻=気のゆるみ」と一刀両断する前に、年齢による体内リズムの差を思い出そう、ということです。若い人ほど夜に向かって元気になる傾向があり、年を重ねるほど朝がラクになる。個人差はあるけれど、ざっくりとした“流れ”はたしかにある。だから、若者の「朝が弱い」を、根性論だけで叱り飛ばしても、むしろ関係を壊すだけになりやすいのです。
「ふるいにかける」やり方は、もう効かない
昔は「遅刻するならクビだ」で回ってしまうほど、若者の供給に余裕がありました。けれど今は違う。とくに肉体労働の求人は、常時“人手不足”が当たり前。塾の現場も同じです。叱って脱落したら、次が無尽蔵に来る時代ではない。だからこそ、「朝に弱い若者」を現実として受け止め、設計側が工夫していく方が、結局は成果につながります。
講習会の時間割、午後起点で組んでみる
稼ぎどきの講習会になると、朝イチからガチッと授業を詰め込みがちです。小学校低学年ならまだしも、中高生にこれをやると学習効率は落ちやすい。私の提案はシンプルです。
午前は自習(来られる子だけ) 朝が得意な子は来ればいい。そうでない子はコンディションを整えてから来る。 授業開始は10時以降、いっそ午後スタートでもいい 夕方〜夜にかけてギアが上がる子が多い。20時に授業が終わっても、若者にとっては「もう寝る時間」ではない。 講師の遅刻リスクも下がる 大学生アルバイトも若者。朝一コマを減らすだけで現場の安定度が上がる。
「朝は自習、午後から授業」。これだけで、居眠り・遅刻・欠席の“理由”がいくつも消えます。結果、学習時間は同じでも、質が上振れする。
親と現場へのメモ
「起きられない=怠け者」と短絡しないこと。無理な早起きを続けると、体調悪化や不登校の引き金にもなり得ます。もちろん、朝に強い子もいます。スタート地点が違うだけで、誰だって年齢とともに少しずつ朝型に寄っていく。 ならば、今この瞬間の“体の都合”に合わせて進め方を調整した方が、成果は出やすい。
まとめ:運営の“引き出し”を一つ増やす
「若者は夜に強い」という前提を持つだけで、時間割、声のかけ方、叱り方が変わります。朝一の授業を“正義”として固定せず、午後起点の設計を引き出しに入れておく。これが、生徒の状態に合わせて成果を最大化する、いまどきの運営だと私は思います。
私自身、この10年で見事に“朝方のおじさん”になりました。だからこそ言えます。努力の問題だけじゃなく、体の仕様もある。そこを認めて設計し直す――それだけで、現場はもっと楽に、もっと伸びます。では、また。

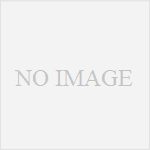
コメント