今日は、昔の職場の塾のホームページを見ていて思い出したことを、メモ的に残しておきます。秋田の状況はなんとなく把握しているのですが、うちは47都道府県に拠点があるので、「他県はどうなってるかな? あの人は今どうしてるかな?」という気持ちで見ていたら、同じ東北のある県の教室で教室長が変わっていました。
その教室はフランチャイズ。直営ではなく、オーナーが加盟料等を払って看板を借りて運営する、コンビニ方式の教室です。私が退職する6年ほど前からその形で回していたはずですが、ここ1〜2年でオーナーが撤退したのか、直営校に戻っているようでした。体感でいえば「10年もたなかった」という印象です。
「有名ブランドの個別指導でも、潰れるところは潰れるんだな」と。最近は、FCオーナーが辞めたあとに、会社の社員がその場所で直営としてやり直すパターンが増えている気がします。ホームページの教室長名が、私の知っている社員に変わっていたので、「あ、FCが畳まれて直営に切り替わったんだな」と察しました。
うまくいく教室/うまくいかない教室の差
私が知る限り、同じ「元社員が独立してFCオーナーになった」例でも、結果は分かれます。関東のとある教室は今もずっと続いていて、生徒数は100名超。オーナー1名(+アルバイトや社員がいる可能性はありますが)でこの規模なら、年収は4桁万円(=1,000万円台)に届く水準です。対して、東北の別の教室は畳まれてしまった。
両者に共通するのは、私が社員時代にやり取りしたことがある、どちらも年上の方だということ。そのうえで、決定的に違ったのは「管理力」でした。うまくいっている方は、県の責任者も務めたことがある優秀な方で、当時から社内データベースを使って情報を可視化し、報告を日次で徹底するなど、管理に異常なほど強い。好き嫌いは別として、「やると決めた管理を最後までやり切る力」がある人です。
一方で、畳まれたほうの教室長は、正直そこが弱かった。心配性というか、いつも誰かに確認しないと前に進めないタイプで、本部のエリアマネージャーにしょっちゅう電話で助言を求めていました。SNS運用もしていましたが、内容が「今日はいい天気ですね」的な雑談で、教室の価値や実績が伝わる発信にはなっていなかった。全体的に「感覚がズレている」印象で、武器になるノウハウも見せられていなかったと思います。
(地域事情として、大学生講師の採用が難しい場所だったのは事実。特に高校生指導の講師確保は厳しい。ただ、映像講座など手段はあるので、やりようはあったはず。ここも結局は管理と設計の問題に帰着します。)
「管理」は好き嫌いではなく結果のための仕組み
私は「成績が上がれば塾は絶対に流行る」と思っています。極論すれば、生徒全員の成績が上がれば潰れません。大手は構造上、全員の成績を常時上げ続けるのは難しい。だからこそ、うまくいっている教室は、管理で“上げる確率”を最大化している。
具体的には、講師に対しても細かく管理します。
「担当生徒の前回テストは何点?今回は? 日々の小テストは実施している? その出題設計は? 模試は春いくつ、夏いくつ、偏差値はどう動いた? 上がった/下がった理由は?」
講師側から見れば小テストをやらないほうが楽ですが、そこを“やる”に寄せて、数値で追い、記録で残す。やり切る図太さ。好きか嫌いかではなく、結果を出すための仕組みです。
個人塾で大切なこと
ただし、個人塾は大手のような過剰な管理は不要です。やることはシンプルで、「全員の成績を上げる」ための最短手段をやるだけ。
英語なら、最初から文法をガンガン…ではなく、本文の音読・暗唱から。驚くほど英語が苦手な生徒は、単語そのものが読めません。読めるようになる → 物語の流れがつかめる → 意味はあとからついてくる。順番を間違えないこと。こうした“順序のノウハウ”を持っているかどうかが勝負です。
うまくいった関東の教室長は、ここも持っていた(あるいは、持っていなくても管理で補っていた)。一方で、東北の教室長は、そのノウハウが見えなかった。ここも勝敗を分けた一因でしょう。
まとめ(メモ)
フランチャイズの個別指導塾でも、潰れるところは潰れる。最近は「FC撤退→直営でやり直し」パターンが目立つ。 勝敗を分けたのは管理力。やると決めた管理をやり切る人は強い。 大手のような“全部やる管理”は個人塾には不要。ただし全員の成績を上げる順序のノウハウは必須。 講師運用は「楽」を排して、小テスト・点数推移・模試結果・原因分析を記録で回す。 SNSは「今日は晴れ」ではなく、**事実ベースの価値(取り組み・成果)**を淡々と発信する。
今日はそんな「潰れちゃった教室」の話でした。どこかの誰かの参考になれば。次回また。

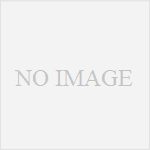
コメント