塾を運営していると、生徒が騒がしかったり、態度が悪かったり、いわゆる「風紀を乱す」という場面に直面することがあります。そういった場合にどう対処するべきか、私なりの結論というか、経験に基づいたお話をさせていただきたいと思います。
世の中には色々な塾がありますが、生徒の言動が原因で大きな揉め事が起きたり、授業妨害をされたりすることがあります。自習室で騒ぐ生徒もいれば、授業中に手紙を回すような、学校でよく見る光景が塾で起こることもあります。
私も経験があります。ある年の中学3年生の男子生徒たちが、少し風紀を乱していた時期がありました。
「静かにしなさい」では、静かにならない
そういう生徒たちに対して、「静かにしなさい」とか「うるさい」と注意するのが正攻法かもしれません。しかし、それで彼らが静かになるわけがありません。皆さんも、自分がやんちゃ盛りの中学3年生だった頃を思い出してみてください。「うるさい」と言われて、素直に静かになりましたか? 表面上は静かにしたとしても、先生が黒板を向いている間にクスクス笑ったり、隠れて何かやったりしていたのではないでしょうか。
指導する側からすれば、体罰はもちろん論外ですし、厳しい言葉がけも推奨されない今の時代、本当に八方塞がりになってしまいます。特に、塾よりも学校の先生の方が、こういった問題への対応は難しいだろうと感じます。
私がたどり着いた最終手段
では、どうしたのか。私が最終的に生徒たちを更生させた(あるいは、しなかった人もいましたが)方法は、学校の先生には絶対にできない手法でした。
それは、「別に、辞めたっていいんだよ」と本気で伝える、ということです。
これは単純なようで、非常に効果があります。
段階を踏んだ、本気の対話
授業を妨害する生徒に対して、いきなりそう言うわけではありません。まずは、1対1で向き合います。5人うるさい生徒がいたら、5人まとめて指導しても意味がありません。膝と膝を突き合わせ、物理的にも、そして心も向き合って本気で話すことで、こちらの言葉が相手に伝わる確率は格段に上がります。
【1回目の面談】
まず、「なぜそういう行動を取るのか」と、理由を尋ねます。
「君の成績が上がらないのは、はっきり言ってどうでもいい。でも、君の行動が他の真面目にやっている生徒たちの成績に影響するかもしれない。その責任をどう取るつもりなんだ?」
私はここまで言いました。ただ一方的にまくしたてるのではなく、「そう思いません?」と相手に問いかけ、考える時間を与えます。沈黙の10秒は、生徒にとって辛い時間かもしれませんが、頭ごなしに言うのではなく、相手の言い分を聞く姿勢を見せることが重要です。
もっとも、授業妨害をする生徒の多くは、「騒ぐのが面白いから」といった程度の理由で、明確な主張を持っているわけではありません。そこで、まずは「行動を改めてほしい」と伝え、約束を取り付けます。
【2回目、そして3回目の面談】
それでも行動が変わらない生徒もいます。2回、3回と面談を重ねても改善が見られない場合、私はこう伝えます。
「無理して、ここの塾に通う必要はないんだよ」
これは本気で、真面目に言います。「辞めろ」ではありません。「騒ぐことでしか、この塾に通う苦痛が紛らわせないのなら、その『塾に通う苦痛』自体を取り除いてあげたほうが、君のためなんじゃないか」と。
「これは本気で君のためを思って言っている。無理してここに来なくていい。俺から親御さんに電話して、事情を話すから」
ここまで言うと、初めて生徒の行動が変わります。「ここが最後の砦だ」と感じるのでしょう。
対話の「証拠」と、その効果
いやらしい話に聞こえるかもしれませんが、これは段階的に対話をしたという「証拠」を残すことでもあります。1回目から「辞めろ」と言えば、ただの感情的な指導です。しかし、何度も膝を突き合わせて話をした上で、「それでもダメなら」という最終手段を提示する。このプロセスが重要なのです。
私がこの方法を使ったのは、ある年の5人ほどの生徒でしたが、結局、全員辞めませんでした。なんやかんやで静かになりましたし、他の生徒に影響が出るほどの騒がしさはなくなったので、水面下での多少のやり取りは放置していました。手のかかる生徒ほど記憶に残る、とはよく言ったものです。
「辞めてもいい」と言う勇気
このやり方のポイントは、「言い方」です。「塾を辞めなさい」ではなく、「無理してここに通わなくてもいいんだよ」と伝えること。「君が苦痛に感じているタスクを、私が親御さんと相談して無くしてあげる」というスタンスで話すのが良いでしょう。
もちろん、それで生徒が本当に辞めてしまえば、塾の売上には響きます。特に会社員の教室長であれば、売上目標があるため、生徒を辞めさせるような対応はしにくいでしょう。
しかし、目先の売上を追うあまり、塾の評判が落ちてしまったら元も子もありません。真面目に勉強している生徒は、必ず親に「〇〇君たちがうるさい」と伝えます。実際に私も、他の生徒から「あの中3の男子たちがうるさいんですけど」という苦情が来ていました。こうなると、もうおしまいです。そうなる前に手を打つべきでした。
学校教育ではできない、民間だからできること
この手法は、学校の先生には使えません。学級崩壊の原因となっている生徒に「明日から来なくていいよ」とは絶対に言えないからです。だから、学級崩壊はなくならない。
学級崩壊を収めるには、原因となっている生徒を物理的に別の場所に移すしかありません。今のクラス、今のメンバーだから、その子はそういう行動を取るのです。別の環境に放り込めば、その子はそこに染まっていきます。
だから私は、年度の途中でクラス替えができない学校のシステムはエラーだと思っています。せめて1年ごと、いや半期に1回クラス替えをすれば、クラス内のヒエラルキーが固定化される前に人間関係がリセットされ、もっと平和になるはずです。
覚悟と副作用
話を戻しますが、「辞めてもいい」と本気で伝えるのは、民間教育機関だからこそできる対処法です。しかし、これを実践している塾は少ないでしょう。なぜなら、保護者からのクレームに繋がるからです。
私も過去に2件、本社を巻き込むほどの大きなクレームを受けたことがあります。「『塾に来なくてもいい』と子どもが言われたが、どういうことか」と。もちろん、言い方に誤解を招く部分があった点は反省しましたが、アプローチ自体が間違っていたとは今でも思っていません。
しかし、多くの教室長はこうしたリスクを避けたがります。使いづらい部下だと思われたくないからです。
最後に
個人塾であれば、悪い口コミは命取りです。たった一人の生徒が原因で評判が落ち、生徒が集まらなくなることは十分にあり得ます。
ですから、塾を運営されている方々へ。
風紀を乱す生徒に対しては、まず本気で対話を重ねること。そして、最悪の場合、その生徒を手放す勇気を持つことも考えてみてはいかがでしょうか。目先の売上やクレームを恐れる気持ちは分かりますが、長い目で見れば、それが塾全体を守ることに繋がるはずです。

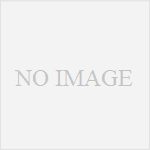
コメント