「塾の自転車置き場の整頓?そんなの当たり前じゃないか」――そう思われる方も多いかもしれません。
確かに、今では多くの塾で自転車置き場の美化が意識されるようになりました。
しかし、その「当たり前」、本当に心の底からその重要性を理解し、徹底できているでしょうか?
実は、今から20年ほど前、私がまだ若手教室長として奮闘していた頃は、これを実践している塾などほとんど見かけませんでした。
もしかすると、何を隠そう、この「自転車スカーン!と整列作戦」は私が発祥かもしれません(笑)。
当時は周囲から「そんなことして何の意味があるんだ?」と不思議な顔をされたものです。
しかし、この一見些細な取り組みにこそ、塾経営を大きく左右するほどの、そして多くの塾長が見落としがちな深遠な意味が隠されているのです。
本日は、この「自転車置き場の整頓」という、ともすれば軽視されがちなテーマを深掘りし、なぜそれが「選ばれる塾」作りに不可欠なのか、その本質に迫ってまいりたいと思います。
第1章:自転車整頓、その「表」と「裏」の本当の価値
自転車置き場を綺麗に保つこと。
これにはもちろん、表向きの分かりやすいメリットがあります。
それは、「生徒たちに整理整頓の習慣をつけさせること」です。
自分の自転車をきちんと並べるという行為を通じて、子どもたちは規律正しい生活態度や、公共の場でのマナーを学びます。
こうした習慣は、やがて学習机の整理整頓にも繋がり、ひいては落ち着いて学習に取り組む姿勢をも育んでいくでしょう。
これは教育的観点からも非常に意義のあることです。
しかし、私がこの「自転車スカーン!作戦」にそこまでこだわったのには、もっと切実な、そして経営に直結する「ウラの理由」があったからに他なりません。
それはズバリ、「客層の質を高めることができる」という一点です。
「客層なんて選り好みしている場合か!」とお叱りを受けるかもしれません。しかし、考えてみてください。
私が考える「流行る塾」の本質とは、例外なく「通った生徒の成績を必ず上げ、全員が志望校に合格させること」です。
この結果を出すためには、どうしたって生徒の入塾時期が重要になってきます。
ハッキリ申し上げますが、本格的な受験学年になってから、慌てて駆け込んできた生徒の成績を、そこから劇的に上げて第一志望校に逆転合格させるなんてことは、並大抵のことではありません。いや、私は不可能だとすら思っています。
それほど、基礎学力の定着と学習習慣の確立には時間がかかるのです。
だからこそ、私たちは本気で生徒の成績を上げたいと願うならば、できる限り早期に、理想を言えば小学校低学年や中学一年生のうちから通っていただく必要があるのです。
そして、この「一年生のうちから塾通いを選択するご家庭」というのは、概して教育に対する意識が非常に高く、学習や受験に対するリテラシーも高い傾向にあります。
第2章:リテラシーの高い保護者は「自転車置き場」で何を見抜くのか
さて、ここからが本題です。
早期からお子様の教育に関心を持ち、情報収集を怠らず、数ある塾の中から「我が子にとって本当に良い塾はどこか」を真剣に見極めようとするリテラシーの高い保護者の方々。
彼女たち、彼らは、一体何を基準に塾を選んでいるのでしょうか?
もちろん、合格実績や指導内容、カリキュラム、月謝といった情報は比較検討されるでしょう。しかし、それ以前に、もっと感覚的で、しかし決定的な「足切り」の判断基準が存在するのです。
それが、「塾の外観、特に真っ先に目に入る自転車置き場の状態」なのです。
想像してみてください。パンフレットでは立派なことを謳っていても、いざ見学に訪れた塾の前に、自転車がグチャグチャに、あたかもゴミのように放置されていたとしたら…?
リテラシーの高い保護者は、その瞬間にこう思うでしょう。
「ああ、この教室のトップである教室長は、この程度の管理能力なのか」
「生徒への配慮や、基本的なしつけすらできていない塾なのだな」
「細部へのこだわりがないということは、きっと指導も雑なのだろう」
「プロ意識が低い。こんなところに、大切なわが子を預けることはできない」
口には出さずとも、無意識のうちにそう判断し、その塾は選択候補から静かに外されていきます。
どんなに素晴らしい指導メソッドを持っていたとしても、どんなに熱意ある講師が揃っていたとしても、その入り口の「自転車置き場」という名の最初の関門で、指導の能力を評価される以前に、候補から除外されてしまうのです。
これは、塾にとってどれほど大きな機会損失であり、残念なことでしょうか。
「人は見た目が9割」という言葉がありますが、塾もまた「外観が9割」と言っても過言ではないのです(少し過言かもですが…)。
第3章:「スカーン!」と並べる技術と、それがもたらす波及効果
では、具体的にどうすれば、自転車を常に「スカーン!」と美しく整列させることができるのでしょうか。
これは決して難しいことではありません。
まずは、白線などで一台一台の停車位置を明確に区切る。
生徒にも分かりやすいように、「ここに前輪を合わせてね」といったイラストや表示をする。
そして何よりも大切なのは、「継続する仕組み」を作ることです。例えば、都度、教室長自らが率先して数台を綺麗に並べ直す。
その姿を生徒や講師が見ることで、「ここはそういう場所なんだ」という意識が自然と芽生えます。
重要なのは、教室の長が「自転車置き場は教室の顔であり、私たちの姿勢そのものである」という強い信念を持つことです。その熱意は必ず生徒やスタッフに伝播します。
そして、この「スカーン!」と並んだ自転車置き場がもたらすプラスの波及効果は計り知れません。
まず、教室全体の美化意識が高まります。自転車置き場が綺麗だと、不思議と下駄箱の靴も揃い、教室内のゴミも減り、掲示物も丁寧になります。
*生徒たち自身も、整然とした環境に身を置くことで、学習への集中力が増し、塾への誇りを感じるようになります。
*保護者の皆様は、その光景を見て、「この塾は細部まで手を抜かない、信頼できる塾だ」という安心感を抱きます。
これこそ、お金をかけずに塾のブランドイメージを高めることができる「ゼロコスト広報」なのです。どんな立派な看板を掲げるよりも、どんな巧みなキャッチコピーを謳うよりも、整然と並んだ自転車の列は、雄弁に、そして静かに、あなたの塾の真摯な姿勢を物語ってくれます。
第4章:小さな「当たり前」が、教室のブランドを創る
自転車置き場の整頓は、数ある「当たり前の徹底」の中の、ほんの一例に過ぎません。しかし、それは塾の理念や教育方針を体現する、非常に象徴的な最初の一歩となり得ます。
「神は細部に宿る」という言葉があります。この精神を、自転車置き場だけでなく、例えば、
生徒や保護者への気持ちの良い挨拶
教室の隅々まで行き届いた清掃
授業や面談の時間厳守
分かりやすく整理された配布物
といった、あらゆる「当たり前」の行動に反映させていくこと。その一つひとつの積み重ねが、やがて指導の質の向上、生徒対応の質の向上へと繋がり、揺るぎない教室のブランドを形作っていくのです。
「そんな細かいことまで…」と思われるかもしれません。
しかし、思い出してください。リテラシーの高い保護者は、その「細かいこと」を実によく見ています。そして、その「細かいこと」をきちんとできる塾こそが、最終的に選ばれるのです。
おわりに
「自転車をスカーン!と並べる」。
この言葉に込めた私の真意、そしてその重要性を、ご理解いただけたでしょうか。
これは単なる美化運動ではありません。生徒の教育であり、保護者への無言のメッセージであり、そして何よりも、私たち塾人のプロフェッショナリズムの表明なのです。
今日から、いや、この記事を読み終えたこの瞬間から、ぜひご自身の教室の自転車置き場を見つめ直してみてください。
そして、もし乱れがあるならば、塾長自らが率先して、一台一台、心を込めて並べ直してみてください。
その小さな行動が、あなたの教室に大きな、そして確実な変化をもたらす第一歩となるはずです。
手間を惜しまず、当たり前のことを、当たり前以上に徹底する。
その覚悟と実践こそが、月謝を払ってでも通いたいと保護者に思われ、地域で圧倒的に選ばれる塾へと成長するための道であると、私は思います。


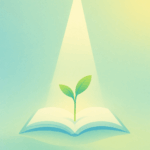

コメント