はじめに
塾を運営していると、同業他社の動向、特にご自身の教室の近隣に新しい塾ができたという情報は、いやが応でも気になるものですよね。「どんな塾だろうか」「生徒、集まるのかな…」。私も、散歩中などに新しい塾の看板を見つけると、つい客のフリをして偵察に入ってしまったことが何度もあります。
しかし、そうしたライバル塾の動向を、単に「敵」や「脅威」として捉えるだけでは、あまりにもったいない。実は、私たちの周りにある他塾、特に「うーん、これはどうなんだろう…」と感じてしまうような塾こそ、自塾を成長させるための最高の「反面教師」であり、最高の「教材」となり得るのです。
今回は、最近私の家の近所にできた、ある中堅塾の教室を題材に、多くの塾経営者が陥りがちな、そして絶対にやってはいけない教室作りの「罠」について、私の経験も交えながら詳しく解説してまいります。
第1章:講師が集まらない教室の「立地の罠」
まず、その新しくできた塾を見て、私が最初に感じた懸念は「講師、どうやって集めるんだろう?」という点でした。その教室は、閑静な住宅街の一角にあり、最寄り駅からはかなり離れています。おまけに、周辺に大学のキャンパスなどもありません。
最近の大学生がアルバイト先を選ぶ基準は、昔とは少し変わってきています。もちろん時給も大切ですが、それ以上に「自宅や大学から近いか」「通学経路の途中にあるか」といった、アクセスの良さを重視する傾向が非常に強いのです。
私が大手塾で教室長をしていた頃も、この「講師の立地問題」には本当に頭を悩ませました。「駅前の〇〇教室なら働きたいけれど、駅からバスに乗る△△教室はちょっと…」という学生さんは、本当にたくさんいました。彼らの言い分も分かります。貴重な時間を割いて働くのですから、移動時間はできるだけ短くしたい。これは当然の心理です。その度に、様々な条件を提示して駅から遠い教室へ行ってもらうよう交渉しましたが、これが本当に大変な仕事でした。
塾の教育サービスの質は、言うまでもなく、指導にあたる講師の質に大きく左右されます。その講師を集める「採用」という入り口の段階で、そもそも応募者が集まりにくいというハンディキャップを背負っている。これは、経営戦略として非常に大きな問題をはらんでいると言わざるを得ません。
「良い先生が来てくれるのを待つ」のではありません。「良い先生が『ここで働きたい』と思ってくれる環境」を、塾側が戦略的に用意しなければならないのです。その第一歩である「立地」の選定でつまずいている時点で、質の高い教育サービスを安定的に提供していくのは、極めて困難な道のりになるでしょう。
第2章:生徒のやる気を削ぐ「空間の罠」
次に私の目に飛び込んできたのは、その教室の「あまりにも殺風景な空間」でした。10畳もないような小さな事務所に、ただ無機質な机と椅子が並べられているだけ。お世辞にも、子どもたちが「ここで勉強したい!」とワクワクするような環境ではありませんでした。
私がこれまで、自転車置き場の整頓や教室の整理整頓の重要性を繰り返しお話ししてきたのは、なぜか。それは、「空間の質」が、生徒の学習意欲や集中力、そして保護者が抱く信頼感に、ダイレクトに影響を与えるからです。
散らかった、あるいは何の工夫もない殺風景な空間は、生徒や保護者に無言のメッセージを発します。「この塾は、私たちのことをあまり大切に考えてくれていないのかもしれない」「ここは、ただ時間を過ごすためだけの場所なのだろうか」と。
もちろん、個人塾などでは、最初から潤沢な資金を投じて豪華な内装にすることは難しいでしょう。しかし、ここで問題にしているのは、お金をかければ解決する話ではありません。生徒が気持ちよく学べるように、少しでも工夫しよう、配慮しようという「マインド」の問題です。
壁に生徒の頑張りを称える掲示物を貼る、観葉植物を一つ置く、参考書をきれいに並べる…。お金をかけずとも、空間の質を高める方法はいくらでもあります。そうした細やかな配慮を怠り、ただ「ハコ」を用意しただけ、という状態は、学習環境という重要な「商品」への投資を怠っているのと同じです。コスト削減を優先するあまり、最も大切な生徒の学習効果を損なってしまっては、本末転倒ではないでしょうか。
第3章:「教育以前の問題」がもたらす致命的な欠陥
ここまで、「講師確保の難しさ」と「学習環境の劣悪さ」という二つの問題点を指摘してきました。厳しい言い方になりますが、これらはもはや「教育以前の問題」です。
そして、私が最も懸念するのは、こうした「教育以前の問題」を軽視している塾は、「必ずや教育面でもショボさが出る」ということです。これは私の長年の経験から来る、一つの確信です。
なぜなら、駅遠の不便な立地を選ぶのも、殺風景な教室環境を放置するのも、その根底にあるのは「生徒のために最高の環境を用意する」という、教育者として、そして経営者として持つべきマインドの欠如に他ならないからです。
講師の働きやすさを考えない。生徒の学びやすさを考えない。そうした姿勢の塾長が、果たして生徒一人ひとりの成績や進路に、真剣に向き合うことができるでしょうか? 私は、極めて難しいと考えます。塾長の持つマインドは、教室の隅々にまで現れます。環境整備に無頓着な姿勢は、やがて指導の質の低下や、生徒対応の雑さといった形で、必ず表面化してくるのです。
おわりに:「最高の反面教師」を活かす視点
「誰が入んねん!」 近所にできたその塾を見て、私は思わずそうツッコミを入れてしまいました。しかし、ただ他塾を批判し、溜飲を下げるだけでは何も生まれません。大切なのは、その「残念な塾」を「最高の反面教師」として、自らを省みるための鏡とすることです。
- 「あの塾のようにはなるまい」という視点で、自塾の立地戦略、講師の採用・定着の仕組みを再点検する。
- 「あの塾のようにはなるまい」という視点で、自塾の学習環境が、本当の意味で生徒のやる気を引き出すものになっているかを見直す。
- そして何より、「あの塾長のようにはなるまい」という視点で、自分自身のマインドが「全ては生徒のために」という一点に向かっているかを常に自問自答する。
他者を観察し、そこから学ぶ。この姿勢こそが、塾運営の能力を高め続ける上で、何よりも重要です。
ちなみに、その塾が万が一、流行ることがあれば、それはそれで最高の教材となります。私が気づかなかった、何か別の成功要因がそこにはあるはずです。その時は、プライドを捨てて、その要因を徹底的に分析すれば良いのです。
常に他者から学び、自らを省みる。その謙虚で貪欲な姿勢こそが、あなたの塾を、地域で本当に選ばれる、永続する塾へと成長させてくれるはずです。

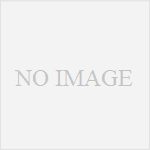

コメント