多くの大手塾では9月が決算月です。私がかつて勤務していた大手塾も例外ではなく、毎年この時期になると「9月30日時点での在籍生徒数」という巨大な目標が、本社からエリアへ、そして各教室へと下りてきました。
「あと10日で10名入塾させろ」——。
そんな無茶な指示が飛び交う中で、現場が編み出してしまった“悪しき技術”があります。それは、本来10月から学習を開始する予定の生徒に、9月中に授業を一度だけ無理やり設定し、帳簿上「9月入塾」としてしまう、いわゆる**「ねじ込み開講」**です。
小売業が決算セールで「お客様が得をする値下げ」を行うのに対し、塾業界のこうした数字合わせは、一体誰が得をするのかすら曖昧です。短期的なノルマ達成と引き換えに、現場の信頼と教育の質を少しずつ蝕んでいく。ここに、教育というサービスの根幹を揺るがす問題が潜んでいます。
期末の数字合わせが、現場の首を絞める
結論から言えば、教育の本質は「成績向上」「志望校合格」「学習習慣の定着」という、生徒の変化そのものです。教室の持つ時間や労力を、この本質的な価値創造にすべて投入できる環境を作れた教室だけが、長期的に地域から支持され、生き残っていきます。
期末に数字を一時的に取り繕っても、その歪みは必ず翌月以降の「学習の質」「生徒・保護者の満足度」「継続率」となって、ブーメランのように返ってくるのです。
決算のプレッシャーが引き起こす現場の副作用は、私がこれまで見てきた中でも深刻なものばかりでした。
まず、前述の**「ねじ込み開講」。翌月からであれば講師の選定や教材の準備、学習計画の策定に十分な時間をかけられるにもかかわらず、月末の数字合わせのためだけに準備不足のままスタートを切らせてしまう。これにより、生徒にとって最も重要な「初回体験の質」が著しく低下します。
次に、実態の伴わない報告業務の増加です。目標達成に向けた電話がけの報告などが形式的に行われ、教室長や講師が本来割くべきであった、生徒一人ひとりの学習設計の時間が無情にも削られていきます。
そして、教室全体が短期的な割引や特典を優先する“営業モード”に偏ってしまう**こと。「なぜ“今”始めると学力向上に繋がるのか」という教育的なきっかけづくりの説明が薄れ、安易な価格訴求に流れがちになるのです。
追いかける目標を“教育の言葉”で見直す
私はこの悪循環を断ち切るため、「数字を作る」という発想を捨て、「成果が自然と積み上がる仕組み」へと教室運営の**“ものさし”**を全て作り変えました。その結果、月末の無理な営業活動は激減し、在籍生の紹介と高い継続率によって教室は安定軌道に乗りました。
教室長が現場でできる具体的な打ち手は、次の通りです。
1. 入会の扱いを“正直”かつ“生徒本位”に
原則として、10月開始の生徒は正直に10月入塾として処理します。その代わり、9月中は「無料の自習室開放」や「学習課題の設計」「三者面談の先行実施」といった形で、学習の価値を“先出し”するのです。そして、「今始めれば、学校の定期テストに〇日前から準備できる」「10月の重要単元の前提となる復習を、9月中に無料で終えられる」といった、学習上のメリットを明確に提示し、生徒の背中を押します。
2. 期末の特典は、学習価値に直結するものに限定する
安易な値引きは、時に授業品質の低下を招きます。特典を付けるのであれば、「テスト対策授業の1回追加」や「個別学習計画の詳細版を無料で作成する」など、成果に近い支援に限定すべきです。
3. 追いかける数字を、営業から教育へシフトする
私が現場で大切にしていた「ものさし」は、以下のような教育を軸にしたものです。
- 最も大切な目標: 定期テストの平均上昇点、志望校合格率、生徒継続率
- 日々の大切な目標:
- 体験から入塾に至る際の「学習価値の理解度」(面談後アンケートで計測)
- 入塾初月の「学習時間の中央値」と「小テストの正答率」
- 入会前・初月末・3ヶ月目といった節目での「面談実施率」
これらの数字を追うことで、教室の関心は自然と「どう売るか」から「どう学力を伸ばすか」へと移っていきます。
4. 9月の“攻め方”を、学習イベント中心に切り替える
月末の駆け込み営業に代わり、「学校別テストの先取り対策会」や「秋の学習計画診断会」といったイベントを企画し、在籍生の成果をどんどん目に見える形にして発信していきます。保護者の許諾を得た上で成果を教室だよりで共有するなど、**“学習の温度”**を上げる活動に注力するのです。結果として、本質的な価値に惹かれた問い合わせが自然に増え、短期の無理な営業は不要になります。
5. 上司への報告を“教育の言葉”で伝える
本社への報告も、「今月入塾〇名」という結果だけでなく、「入塾者の初月学習時間の中央値」「初回面談の実施率100%」といった教育活動の指標を並べて報告します。たとえ入塾目標が未達でも、「初月の学習の定着をしっかり行った結果、3ヶ月後の継続率が向上し、生徒さんが長く通ってくれることで将来の教室の利益に繋がります」というように、長期的な視点で説明するのです。
個人塾の強さと、大手塾が勝つための道
個人塾の強みは、教室長が最終的な判断を下せる立場にあり、教育という本質に全ての力を注ぎやすい仕組みにあります。しかし、大手塾の教室長であっても、本社から与えられた数字目標を現場の“教育の言葉”に置き換え、学習イベントと面談の質で価値を積み上げることで、短期ノルマに振り回されない強固な教室を作り上げることは十分に可能です。
まとめ:期末に“作る”のではなく、毎日“積む”
決算月という節目は、数字に追われる時期ではなく、学習の成果を高めるための“追い風”として利用すべきです。
入会の扱いは正直に、しかし価値は前倒しで提供する。教室が目指す目標は、生徒の学習時間や定着率を中心に据え、上司への報告も教育の言葉で語る。
短期的な数字は、あくまで日々の正しい教育活動の“結果”として後から付いてくるもの。期末に無理をして数字を作るのではなく、毎日の学習設計で成果を積み上げる。これこそが、長く地域から支持される教室運営の、唯一の近道だと私は確信しています。


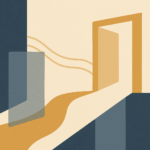
コメント