「時給は、生徒の成績を上げるという目的を達成した“結果”に過ぎない」
全国でも有数の大規模教室を、正社員である私一人と最大70名の大学生講師で運営していた頃。私は、自他ともに認める“規律にうるさい教室長”でした。おそらく、鬱陶しいとさえ思われていたでしょう。
しかし、私はあえてその役割を引き受け、言い切ることをやめませんでした。
今回は、私がなぜそこまで規律にこだわったのか。その背景と具体的なルール、そしてルールによって何が得られたのか、そのリアルをお話しします。
1. 教室が大きくなるほど、魂は細部に宿る
若い頃の私は、典型的な“お兄さん的”な教室長でした。講師や生徒と年齢が近いこともあり、親しみやすさを前面に出し、和気あいあいとした雰囲気を作ることに注力していました。
しかし、それは大きな間違いでした。
距離が近い分、空気は一時的に和らぎます。しかし、それは「なあなあ」な関係への入り口に他なりません。基準は曖昧になり、指導の質は講師個人の裁量に丸投げされ、やがて運営そのものが崩れていくのです。
30代に入り、私は方針を180度転換しました。
塾の本質はただ一つ、「生徒全員の成績を上げ、志望校に合格させること」。この絶対的な目的に向けて、全員の矢印を揃える。そのために、場の規律を“意図的に”設計し直すことにしたのです。
2. ルール①:外見の統一は「市場への宣言」である
まず着手したのは、講師の「見た目」です。
採用段階で、髪色の染色は禁止(当時)、ネックレスやピアスといったアクセサリー類も勤務中は一切不可と伝えました。
これは、誰かの個性を否定したいからではありません。
私たちの教室が、「本気(ガチ)の講師しかいない、学力を上げるためのプロ集団である」というメッセージを、教室の内外に一貫して示すためでした。
個別指導塾の顧客、特に私たちがメインターゲットとすべき経済的に余裕のあるご家庭は、人を見る目に長けています。そして、人の本質の一端が服装や身だしなみに現れることを、感覚的に知っているのです。
個別指導は、“人”そのものが商品です。講師の第一印象を高いレベルで統一することは、品質管理そのものなのです。
3. ルール②:挨拶は“所作”まで含めて型にする
「こんにちは」「お疲れさまでした」。
言葉にするのは簡単ですが、その実態は驚くほどバラバラです。
だから、私の教室では“所作”までを一つの型にしました。
- 出勤時: ドアを開けたら一度立ち止まり、姿勢を正して「こんにちは」。
- 退勤時: 教室全体を見渡し、「お疲れさまでした」と言い切ってから一礼。
- 保護者対応中: 私が受付で保護者と話している背後から入室する際は、保護者にもはっきりと聞こえる声で挨拶する。
ここまで徹底する理由は、至ってシンプルです。
上質なサービスに慣れた方ほど、“挨拶がない”という些細な点を見逃しません。挨拶が「当たり前」の空気を作ることは、不要なクレームを未然に防ぐ最強の予防策であり、口コミで信頼が広がっていくための最短ルートでもあるのです。
4. ルール③:授業の“途中経過”まで見せる。それが本物の証
「いつでも、どの授業でも見学なさってください」
私は入塾面談の最後に、必ずこの言葉を添えて教室内をご案内していました。
多くの塾がこれをためらうのは、授業の“途中経過”を見せる自信がないからです。しかし、私は発想を逆転させました。
“常に見せられる現場”を作るために、規律を敷くのだ、と。
いつ、誰に見られても恥ずかしくない。講師は常に背筋を伸ばし、生徒は真剣に問題と向き合っている。整理整頓された空間には、心地よい緊張感が漂う。
あえて全てを公開する設計に振り切った結果、「この塾は裏表がない」「安心してお任せできる」という、何よりも強い評価をいただくことができました。
5. なぜ、教室長は「嫌われ役」を引き受けるべきなのか
講師には、繰り返しこう伝え続けました。
「君たちの仕事の目的は、時給をもらうことじゃない。生徒の成績を上げることだ。時給は、その目的を達成するための行動を積み重ねた“結果”に過ぎない」
耳ざわりの良い言葉ではありません。反発もあったでしょう。
だからこそ、この「嫌われ役」は教室長が引き受けなければならないのです。
目的が一致しない組織は、いずれ本社の営業目標や目先の売上のために、不正な“ねじれ”を生みます。生徒のためではない、会社のための面談や講習提案が横行するようになる。大教室ほど、その腐敗の兆候は早く、そして大きくなるのです。
6. ルールが生んだ“最高の副作用”
もちろん、厳しさを嫌って去っていく応募者もいました。
しかし、それでいいのです。基準とは、“入口の段階で、同じ目的を共有できる仲間だけを残すためのフィルター”でもあるからです。
結果として何が起こったか。
指導の質、教室の雰囲気、そして保護者の安心感が、面白いようにそろって向上し、現場はむしろ格段に回しやすくなりました。
人数が増えるほど、規律は自由の敵ではありません。
自由に、そして最大限に成果を出すための“走行レーン”になるのです。
7. 結論:うざいと言われようと、本質に忠実であれ
私が敷いた規律は、誰かを縛り付けるためのものではありません。
ただ一点、「生徒の成績を上げる」という塾本来の目的に、どこまでも忠実であるための構造です。
講師70名の大教室であっても、気持ちの良い挨拶が響き渡り、講師の姿勢は常に正され、いつ見られても困らない緊張感がそこにある。そんな現場は、必然的に保護者の信頼を呼び込み、結果として生徒の学びを力強く前進させます。
私が“規律にうるさい教室長”という役割を甘んじて引き受けたのは、全て、生徒の「合格」という最高の結果に、徹頭徹尾こだわり抜きたかったからです。

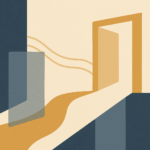

コメント