1. きっかけ:あるSNS投稿への違和感
先日、ある女性のSNS投稿が目に留まりました。
内容は、彼女の職場に年上の男性社員(おっさん)が入社し、自身が指導係になったというものです。しかし、その男性はメモも取らず、物も覚えず、挙句の果てには「教え方が悪いから覚えられない」という態度だったそうです。結局、その男性はすぐに辞めてしまい、彼女は「指導に費やした時間が無駄になった。時間を返してほしい」と嘆いていました。
この投稿に対して、多くの人は「それは大変でしたね」「頑張りましたね」と彼女に共感するでしょう。もちろん、その気持ちも理解できます。
しかし、私が感じたのはそこではありませんでした。私が抱いたのは、「そもそも、なぜ企業はそんな人物を採用したのでしょうか?」という一点に尽きます。
2. 問題の本質はどこにあるのか:「他責」から「自責」へ
この件で、辞めていった男性を責めても何の意味もありません。彼は採用面接を受け、採用され、合わないと感じて退職しました。法を犯したわけでもなく、ただ権利を行使しただけです。「あのおっさんは何だったんだ」と不満を言っても、それこそ時間の無駄です。
問題の本質は、明らかにやる気のない人物を見抜けず、採用してしまった「企業側」にあります。これは採用側の責任であり、ある種の「自業自得」なのです。
本当にこの問題を解決し、再発を防ぎたいのであれば、考えるべきは「どうすれば、こういったミスマッチを防げるか」という点です。採用基準を厳格にする、面接だけでなく実技試験や適性検査を取り入れるなど、採用プロセスそのものを見直す必要があります。そうしなければ、企業は永遠に「採用ガチャ」「人材ガチャ」という運任せの状態から抜け出せません。
3. 思考の展開:塾の指導者としての立場から
この「自責思考」の考え方は、私の本業である塾の仕事において、極めて重要になります。
私たちの仕事は、生徒の成績を伸ばすこと、つまり生徒の「行動」を変えることです。しかし、実際に行動するのは生徒自身であり、我々ではありません。ここが難しいところです。
スポーツジムのトレーナーが、会員の代わりに運動するわけではないのと同じです。ただし、ジムは「自己責任」で通う大人が相手ですが、塾は違います。お金を出すのは「親」、学ぶのは「子供」、そして指導するのが「塾」。この三者が関わる複雑な構造の中で、結果を出す責任が我々にはあります。
生徒の成績が上がらない時、「生徒にやる気がないから」「生徒が勉強しないから」と他責にするのは簡単です。しかし、本当に考えるべきは「自分の指導方法は正しかったのか?」「もっと良いアプローチはなかったか?」という振り返り、つまり「自責」の視点です。
4. 具体例:自責なき指導者の末路
残念ながら、教育現場にはこの自責の視点が欠如している指導者が存在します。特に、昔ながらの集団指導塾には、自分の指導方法を一切振り返らず、20年前と同じやり方を続けている者がいます。
私が以前いた会社にも、生徒の点数が悪いとクラス全員の前でその生徒の点数を公表し、罵倒するような人物がいました。それは指導ではなく、間接的な体罰に等しいです。そんな指導で生徒の成績が上がるはずがありません。たまたま優秀なクラスを受け持てば結果は出るかもしれませんが、それは指導者の実力ではありません。塾の仕事とは、本来、塾の助けがなければ成績が上がらない生徒を、いかにして伸ばすかにあるはずです。
時代は常に変化しています。5年前の中学生と今の中学生とでは、TikTokや生成AIの存在が当たり前になっているように、価値観も感覚も全く違います。それに合わせて、指導のアプローチ、言葉の選び方、生徒との接し方もアップデートし続けなければなりません。
5. 結論:全ての事象は自分に起因する
冒頭のSNSの事例に戻りますが、「変な新入社員のせいで時間を無駄にした」と考えていること自体が、思考としていい方向ではない、と私は思います。
人の悪口や不満を言うと、そのマイナスの感情は、言われた相手以上に、言った本人の脳に蓄積されるといいます。脳は、その悪口が誰に向けられたものか区別できず、ただネガティブな感情だけが自分の中に積み重なっていくそうです。良いことなど一つもありません。
逆に、人を褒めると、そのプラスの感情が自分にも返ってきます。だからこそ、私は生徒にも、自分の子供にも、マイナスな言葉は一切使わないようにしています。
最終的に、私が伝えたいことは2つです。
1. 根本を突き詰めましょう。
表面的な出来事や他人の行動に文句を言うのではなく、なぜそれが起きたのかという根本的な原因を探ることです。
2. 自責思考でいきましょう。
全ての事象は、何らかの形で自分の行いや選択が影響していると捉えることです。他人がこうしたから、ではなく、その状況に対して自分はどうすべきだったのかを考えることです。
これが、あらゆる問題を解決し、自分自身を成長させるための、最も重要な思考法だと考えています。

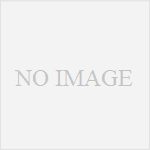
コメント