こんにちは。
今日は、大手塾、特に個別指導塾に通われている生徒さんや保護者の方から、本当によく聞くご不満について掘り下げてみたいと思います。
それは、「せっかく授業に行ったのに、自習と同じだった」というお声です。
授業時間(例えば90分)のうち、ほとんどが問題を解いているだけで終わり、解説はごくわずか。これでは高い授業料を払う意味がない、と感じられるのは当然のことです。
集団指導塾でも稀に聞かれますが、特に個別指導塾でこの不満は頻繁に発生します。 なぜ、このようなことが起きてしまうのでしょうか。
その最大の理由は、授業を担当する講師(多くは大学生のアルバイトです)が、「授業の組み立て」を事前にしていないからです。
具体的には、 ・次の授業で何を扱うのか、事前の予習をしていない。 ・この授業の終わりまでに、生徒をどの状態まで引き上げるのか、というゴール設定がない。 ・生徒がどこでつまずきそうか、という想定ができていない。 といった点に尽きます。
特に、世の中の個別指導塾の多くは「講師1人に対して生徒2人(あるいは3人)」という形式です。 講師が、生徒一人ひとりの学力特性(どこが苦手か、など)を把握しないまま授業に臨むとどうなるでしょうか。
例えば、Aさんの解説に想定外の時間がかかってしまった場合、もう一人のBさんは、その間ずっと放置されてしまうのです。 これが「自習と同じ」状態の正体です。
もちろん、成績を上げるためには、生徒自身が「ああでもない、こうでもない」と考え抜き、あがく時間も絶対に必要です。 ただ、私は「その時間を、授業中に設定する必要はないのでは?」と考えます。
例えば、授業が始まる前の30分間に集中して問題を解く時間を設けるなど、やり方は工夫できるはずです。 しかし、学生アルバイトの講師にそこまでの授業設計を求めるのは難しいのが現状です。
さらに深刻なのは、講師自身が「何を準備したらいいのか分からない」という問題です。
突然話題が変わりますが…例えば、アパレル業界の新入社員に「街に出て、今の服装の傾向を報告してください」と漠然とした指示を出しても、良い報告は期待できません。 ですが、「黒い服を着ている人が何割いるか数えて、そこから分かることを考えてください」という具体的な「視点」を与えると、彼らは動き出せます。
塾の講師も同じです。 「授業準備しなさい」ではなく、「前回A君がどの問題でつまずいたか確認して」「今日の問題で苦戦しそうな箇所を3つ予想して」「その解説に時間がかかりそうなら、どこまでを今日のゴールにするか決めておいて」といった、具体的な「視点(指示)」が必要です。
本来、この指示を出すのが教室長の役割です。 しかし、大手塾の多くは、教室長自身がその指導ノウハウを持っていない、あるいは、持っていても多忙すぎて実行できないケースが非常に多いのです。
私自身も大手塾にいましたが、一部の優秀な教室長が素晴らしいノウハウを持っていても、上層部がそれをヒアリングして組織全体で共有しよう、という動きはありませんでした。
つまり、大手塾では「どの教室長にあたるか」という運の要素が強くなってしまいがちです。
だからこそ、私は今、個人塾の先生方に大きな期待を寄せています。
個人塾は、大手のような仕組みの制約がありません。良くも悪くも「力技」で、目の前の生徒たちとことん向き合うことができます。 その中で蓄積されたノウハウこそが本物です。
大手塾にはない柔軟さと情熱をもって、地域の子供たちの成績を本気で上げる。そうした個人塾の役割が、今ますます重要になっていると感じています。

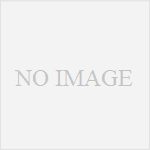
コメント