「電話は3コール以内に出なさい!」
かつて私が大手塾に勤務していた新人時代、最初に徹底されたルールがこれでした。
電話が鳴ったら、文字どおり“這ってでも”取るように言われていたのをよく覚えています。
理由は明快で、「4コール目以降、お客様は『誰も出ないのか?』と不安になる」から。電話対応のスピードが、塾の信用に直結する——それがその塾の教えでした。
もちろん、その意図自体は理解できます。問い合わせをした保護者が電話口で不安になるのは避けたい。だから即応する。顧客対応として正しい姿勢だと思います。
けれど、今、教室長という立場で日々の現場に立っていると、私はあの頃の教えに対してこう思うのです。
「本質からズレていないか?」
電話対応よりも、目の前の生徒
たとえば、今まさに教室で生徒と向き合っているとき。
勉強の悩みを真剣に話している生徒が目の前にいる。あるいは、保護者面談で進路について話し込んでいる最中。そんなときに電話が鳴ったとしたら——あなたはどうしますか?
3コール以内に出ることが「正解」なのでしょうか?
私は、そうは思いません。
塾の本質的な価値とは、「今いる生徒の学びと成長にどれだけ向き合えるか」にあります。
電話はあくまで“外の入り口”です。それよりも、今目の前にいる“中のお客様”の満足度、安心感、信頼感を高めることのほうが、よほど優先されるべきです。
“這ってでも電話に出ろ”という考えの限界
もちろん、電話対応をおろそかにしていいと言っているわけではありません。
ただ、「電話を優先するあまり、本当に守るべきものを見失っていないか?」という問いかけをしたいのです。
今や、お問い合わせ手段も多様化しています。メールやLINE公式アカウントなどを通じて、非同期的にやりとりすることも一般的になっています。仮に電話にすぐ出られなかったとしても、後ほど折り返せば多くの場合問題はありません。
つまり、「3コール以内に出る」ことそのものが目的になってはいけないのです。
本来、私たちの仕事は「問い合わせに素早く出る」ことではなく、「生徒の成績を上げること」。
その目標に照らして、「今、自分が何を優先すべきか?」を冷静に判断できることが、教室長に求められる視点なのです。
すべての行動を“成績向上”に結びつけよう
私がいつもスタッフに伝えているのは、「その行動が、生徒の成績向上につながっているか?」という問いを常に持っていてほしいということです。
自習室で生徒が集中できるように環境を整える。
講師が生徒一人ひとりに向き合えるようにサポートする。
保護者との面談で信頼を深める。
これらはすべて、教室長の大切な仕事です。
そして、こういった“教室の中”にいる人たちに向けた時間やエネルギーこそが、成績向上という結果に直結します。
電話対応もその一部にはなり得ますが、電話のために生徒対応を中断するようでは本末転倒。
目先の形式的な「ルール」を守ることではなく、大局的な視点で判断することが求められています。
教室運営における“芯”を持とう
私たち塾人は、毎日多くの判断を迫られます。
今この場面では、生徒との対話を優先すべきか?
この業務は本当に必要か?
自分の行動は、生徒のためになっているか?
このような問いに対し、自信を持って判断するには、「教室運営の軸=芯」を持っている必要があります。
それは、売上でもなければ、マニュアルでもない。
**“生徒の学びにとって最良の選択かどうか”**という視点こそが、教室長の行動原理であるべきです。
その芯があれば、仮に電話にすぐ出られなかったとしても、教室の信頼は揺るぎません。
逆に、芯がなければ、いくらマニュアル通りに動いても、保護者や生徒には伝わらないのです。
「電話に出るか?」ではなく「今、何が最優先か?」
これからの教室運営に求められるのは、形式にとらわれない柔軟さと、判断の基準を持つ力です。
もちろん、電話に出ることを軽視していいわけではありません。
でも、それよりももっと大事なものがある場面では、迷わずそちらを優先していいのです。
「3コール以内に出るべし」という昔ながらのルールに縛られすぎず、「今この判断が、生徒にとって、教室にとって、ベストか?」という視点を常に忘れないようにしましょう。
そして、教室長として、自分なりの“芯”を持ち、ブレずに教室運営をしていきたいものです。

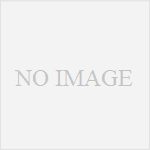
コメント