塾の教室を運営していると、毎年のように現れます。
「何だか話しかけづらいな…」と感じる生徒。
こちらが声をかけようとすると、どこか壁を作っているような雰囲気を漂わせる。
反応が薄かったり、目を合わせなかったり、無口で表情も乏しかったり。
「話しかけるなオーラ」とでも言いたくなるような空気感に、教室長としてもつい気後れしてしまう。
そんな経験、きっとどなたにもあるのではないでしょうか。
「話しかけられたくない」と思っているのか?
たしかに、その日その瞬間、「誰とも話したくない」と思っている生徒はいるかもしれません。
反抗期の最中かもしれないし、家庭や学校で何かあって落ち込んでいることもあるでしょう。
ですが、それが“いつもずっと”なのかというと、そんなことはほとんどありません。
むしろ私は、「塾の先生に話しかけられたくない生徒」なんて、基本的には存在しないと思っています。
だってそうですよね?
塾に通い、自習までするというのは、それだけ「勉強に向き合おう」としている証拠です。
誰にも関わりたくないなら、そもそも塾には来ないはずです。
それでも距離をとっているように見えるとしたら、それは表現の不器用さだったり、緊張だったり、ただのタイミングの問題だったりするだけなのです。
話しかけないことの“代償”は想像以上に大きい
こうした生徒を、「何となく苦手」「話しかけづらい」と感じるがゆえに放置してしまうこと。
これは、教室長として最も避けるべき判断です。
なぜなら、見た目には「手がかからない」ように見えるその生徒が、実は独りよがりな学習法に走っている可能性が非常に高いからです。
誰とも相談せず、自分なりのやり方で黙々と勉強を進める。
ノートもきれいにまとめていて、真面目そうに見える。
でも実は、演習量が足りていなかったり、解き方の癖が強かったり、進度がバラバラだったり。
そんな“孤独な学習”の末に待っているのは、受験の失敗です。
最悪のケースは、誰にも頼れず、気づけば取り返しのつかないズレが生まれてしまっていた——というもの。
そのリスクを防げるのは、教室長であるあなただけなのです。
苦手な生徒を“作らない”という覚悟
私たちは指導者である以前に、教室を預かる責任者です。
「なんか話しかけづらいなー」
「今日は声をかけるのをやめておこう」
「この子はあまり関わらない方がよさそう」
そんな判断を、一教室の責任者である教室長がしてしまってはいけません。
たしかに全員と同じ距離感を保つことは難しいかもしれません。
でも、「苦手だから距離を置く」という選択をしてしまったら、その瞬間にその生徒との信頼構築の芽は摘まれてしまいます。
どんな生徒にも声をかける。
反応が薄くても、態度が素っ気なくても、根気強く向き合い続ける。
その積み重ねが、生徒の心を開かせ、受験の成功を後押しする力になるのです。
合格しても「感謝されない」未来
仮に、そうした生徒が第一志望に合格したとしても、関わりを持たなかった塾に対して「あの塾のおかげで合格した」と思うことはないでしょう。
塾というのは、単に問題を解くだけの場所ではありません。
自分の努力を見てくれていた人がいた、支えてくれた人がいた——その実感があるからこそ、生徒の心に“居場所”として残るのです。
「この塾で頑張れてよかった」
「先生がいてくれたから乗り越えられた」
そう思ってもらえる塾であるためには、どんな生徒にも話しかけ、関心を持ち続けることが必要不可欠です。
最後に:あなたの言葉を、生徒は待っている
話しかけづらいと感じる生徒がいたら、まずは心の中でこう問いかけてみてください。
「この子は、本当に話しかけられたくないのか?」
おそらく、答えは「いいえ」です。
きっとその子も、誰かに声をかけてほしい。見ていてほしい。評価してほしい。
ただ、それをうまく表現できないだけなのです。
教室長であるあなたの言葉は、生徒にとって想像以上に大きな力になります。
ぜひ今日も、あのちょっと距離のある生徒に、一言でも声をかけてみてください。
あなたの助けを、生徒は必要としているのですから。

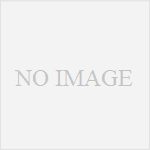
コメント