塾の現場で生徒と日々向き合っていると、ふとした瞬間に気になることがあります。それが「生徒の呼び方」。
講師が生徒の名前をどう呼んでいるか──これは、意外と教室の空気に大きな影響を与えるポイントです。中には「そんなの細かいことじゃないか」と思う方もいるかもしれません。でも、私はこの“呼び方”こそが、生徒との距離感、講師の在り方、そして教室文化の軸を作るとさえ思っています。
「ちゃん」付けは親しみ?それとも…
女性講師、とくに学生講師が、生徒を「○○ちゃん」と呼んでいる場面を見かけることがあります。親しみを込めて呼んでいるのは分かるし、本人たちも悪気があるわけではありません。でも、ここで立ち止まって考えてみたいのです。
「ちゃん」付けって、誰にでも自然にできる呼び方でしょうか?
答えはおそらくNOです。実際には「そう呼びやすい雰囲気を持っている生徒」にだけ「ちゃん」付けがされてしまう。つまり、講師側の印象や感覚で、生徒によって呼び方が変わってしまうのです。
これは、教室の中に“無意識の差”を生む原因になります。
講師は悪意がなくとも、「この子は話しやすいから“ちゃん”」「この子は少し壁があるから“さん”」といった具合に、生徒によって態度に差をつけてしまいかねません。こうなると、生徒の間にも微妙な温度差が生まれます。本人が気づいていなくても、「私ってなんとなく距離を取られてる?」と感じる子が出てくるんですね。
そしてなにより、講師自身の“生徒への接し方”が曖昧になります。
「親しき仲にも一線あり」を徹底する
私はこれまで、教室の方針として、呼び方にはルールを設けてきました。
-
男子生徒には「○○君」
-
女子生徒には「○○さん」
-
呼び捨ては原則禁止
シンプルですが、これだけでずいぶんと教室の空気は整います。大学生講師にとっても、「あの子だけ“ちゃん”って呼んでたけど…」と悩む必要がなくなりますし、指導者としてのけじめを持ちやすくなる。
もちろん、「でも“ちゃん”の方が打ち解けやすいですよ」という声も分かります。でも、私があえてルールを設けている理由は、“講師と生徒が友達にならないため”です。
特に大学生講師の場合、生徒との年齢が近いぶん、距離が縮まりやすい。そのぶん、曖昧な接し方になりやすい。「友達みたいな先生」は、表面上は人気者に見えますが、実は指導力が発揮しづらい立場でもあります。導けない、頼られない──結果、生徒の成長の妨げになってしまうことも。
「先生」としての立ち位置を守るためにも、「呼び方」は立派なツールのひとつなのです。
私が「名前」にこだわる理由
ちなみに、私自身は生徒を下の名前で呼ぶことにこだわっています。
理由はシンプルです。名前には、その子の親御さんやご家族の想いが詰まっているからです。
ときには珍しい読み方の名前に出会うこともありますが、それもまた一つのアイデンティティ。本人にとっては自分を象徴する、たった一つの言葉です。だからこそ私は、その名前を大切に扱いたいし、本人にも「自分の名前っていいな」と思ってほしい。
この“名前を大切にする文化”もまた、教室の根っこの部分に関わってくると感じています。
大人数教室ほど「些細なルール」が大切
生徒数が多くなればなるほど、教室内の一体感や秩序を保つのは難しくなります。講師の数も増え、関わる人も多様になる。
だからこそ、「呼び方」という細部へのこだわりが、教室運営の安定につながるんです。
逆に、細かな決めごとを軽視していると、大規模な教室ほど中身がバラバラになりやすい。崩壊の兆しは、たいてい「まあ、いいか」で始まります。
呼び方を統一することで、教室の一体感が生まれ、講師間の教育方針も揃います。つまり、些細に見えるけれども「講師の質を支えるベース」になっているのです。
まとめ:名前の呼び方は、生徒への“敬意”そのもの
講師が生徒をどう呼ぶか──それは、単なる言葉選び以上の意味を持ちます。
それは、「あなたを一人の人格として見ていますよ」という、敬意の表れです。
親しみを込めながらも、節度ある距離を保つ。
そのバランスを作るために、呼び方のルールはとても大切です。
もしあなたの教室で、呼び方にばらつきが出ているようであれば、ぜひ一度、見直してみてください。「え、そこから?」と思われるかもしれませんが、こういうところこそが、実は教室文化の基盤になるものです。
そしてそれが、生徒にとって居心地のいい場所を作る第一歩になると、私は思っています。

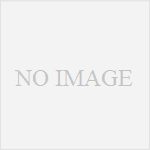
コメント