季節講習前になると、大手塾の現場はざわつき始めます。
「全保護者と面談をせよ」――本社からのお達しが飛ぶのです。
目的は、言わずもがな。
季節講習を取ってもらうためです。
これはもう、どこの大手塾でもある“風物詩”のようなものかもしれません。
もちろん、講習を取ってもらうことそれ自体は悪ではありません。
しかし、問題はその面談の「質」と「目的」です。
私自身、かつてはこの全保護者面談を何の疑問も持たずに実行していました。
ですがあるとき、ふと立ち止まって気づいたのです。
「この面談、保護者にとって本当に意味があるだろうか?」
面談の「義務化」は信頼を損なう危険すらある
毎年のように、講習前のこの全体面談をこなしていると、
次第に「こなす」ことが目的化してきます。
・スケジュールを埋める
・話す内容をテンプレート化する
・とにかく人数をこなす
こうなってくると、面談そのものが薄っぺらくなるのは当然です。
さらに悪いことに、保護者の中にはこう思う人も出てきます。
「また講習の営業か…」
「この人、うちの子のこと全然わかってないな…」
本来、保護者との面談は「信頼を積み重ねる場」であるはず。
なのに、「売上のための場」にすり替わってしまっては本末転倒です。
「希望制面談」という選択
私はある年から、思い切って保護者面談を「希望制」にしました。
本社の方針には反していたので、正直、勇気の要る決断でした。
でも結果的には、この選択が教室を救ってくれました。
面談の数は当然減りました。
しかし、それによって一つ一つの面談にかける時間と熱量が増しました。
準備も入念に行えるようになり、資料も個別最適化できる。
保護者にとっても「自分のための時間」になったのです。
そしてなにより、保護者の反応が明らかに変わりました。
「話をしに来てよかったです」
「こちらの話をちゃんと聞いてもらえたと感じます」
以前よりもむしろ、講習提案の受け入れ率は上がりました。
教室長が「やらされる面談」は、信頼を削る
塾においては、売上は重要です。
でも、売上は「信頼の蓄積」の結果であって、目的ではありません。
保護者面談が「営業の場」として先鋭化していくと、
本来あるべき「信頼構築の場」としての価値が失われます。
教室長が面談を「やらされる」ものとして捉えてしまうと、
準備も雑になり、言葉も響かなくなります。
保護者の心にも、確実にそれは伝わってしまうのです。
面談を「量」から「質」へ
私が声を大にして言いたいのは、
面談はやればやるほど良いわけではないということ。
むしろ、「やらなくていい面談」もあるのです。
保護者にとって、無意味な時間を強いられることほど不信感を招くことはありません。
教室側も疲弊します。
疲れた顔で惰性の面談をしても、何も生まれません。
だからこそ、
「全保護者と面談を!」という号令には、
現場の教室長が一度立ち止まって考える必要があります。
本当にこの面談は、保護者と生徒のためになるのか?
教室の信頼を積み上げる機会になり得るのか?
まとめ
保護者面談は、営業のための「義務」ではなく、
信頼を築くための「選択肢」であるべきです。
その選択の自由を教室長が持ち、
「やるべき面談」に集中することで、
結果的に教室全体の価値も、売上も向上していく。
画一的な施策が現場に合うとは限らない。
むしろ、現場の肌感覚で変えていけることこそ、教室長の醍醐味ではないでしょうか。

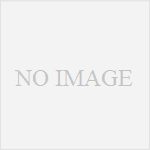
コメント